再生不良性貧血でシクロスポリン内服中のノカルジア肺炎の症例を見たのでまとめてみます
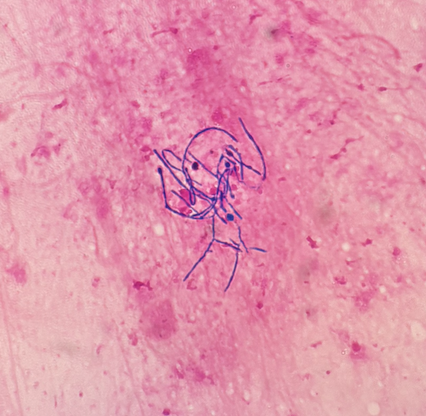
⚫︎ノカルジア肺炎のコンサルトでは何をチェックするか?
① 細胞性免疫不全や肺の構造的異常があるか
局所感染は明らかな細胞性免疫不全がなくとも生じうるとされますが、古典的には細胞性免疫不全患者に見られる疾患です。
PSL≧20mgを1ヶ月以上はアウトと言われますが明確なカットオフはなく、シクロスポリン/タクロリムス、アレムツズマブ、イブルチニブ、リツキサン、抗TNF-αなどもリスクと知られているようです。
② 病歴がノカルジアで良さそうか
今回の再生不良性貧血+シクロスポリンの症例は、2週間の経過で発症していました。教科書的には亜急性で数週間の経過と記載されており、症状は肺炎として非特異的なものがメインです。本症例は吸気時の胸痛はあり、血痰は認めませんでした。
③ 播種性病巣はないか
注意すべきは脳、肺、皮膚が3大病変、加えて眼(直接浸潤 or 血行性播種)や骨/関節、肝脾や前立腺などの膿瘍なども生じうるとされています。皮膚と神経所見をしっかりチェックして、頭部MRIは免疫不全者ならルーチンに行っても良いとされています。傷があればそこのスワブ培養を出してみてもいいかもしれません。
④ その他のOI合併も注意する
免疫不全者であり複数病態が同時に問題を起こしている可能性もある、糸状菌培養や抗酸菌培養はしっかり確認しておくのが良いと思われます。
⑤ ガーデニングなどの暴露歴はあるか
ガーデニングや外傷、建設業などの粉塵に暴露する場合も感染リスクとなる。院内感染のアウトブレイクもあるらしいです。
⚫︎ノカルジア肺炎の治療のポイントは何か?
・治療レジメンをどうするか
ノカルジア感染症の治療レジメンについての確固たる比較試験はないですが、原則としてinduction therapyはdual therapy(皮膚局所であれば単剤でもOK、中枢神経は3剤)で、経験的にはST合剤、イミペネム/メロペネム、アミノグリコシド、リネゾリドが信頼されている薬剤になります。
induction therapyを決めるポイントとしては、疫学データと副作用の懸念がどれくらいあるかを考えます。本邦で比較的多いN.farcinicaはST耐性のリスクがあり(3-4割)、本邦ではイミペネム+アミノグリコシドというレジメンも良いかもしれません。ST合剤は腎障害、イミペネムは脳病変があった場合に痙攣リスクがあり、アミカシンは耳毒性/腎毒性に注意が必要です。腎機能に懸念があれば、リネゾリドは選択肢かもしれませんが、血液疾患の患者では血小板減少により注意が必要であり、これらを総合的に考えてレジメンを選択します。
感受性が判明すれば、それに応じて単剤治療へとスイッチしていくことになりますが、ノカルジアの菌種同定/感受性検査は検査室によっては困難な場合があり、注意が必要です。質量分析は比較的同定に有用な可能性があり、亜種同定から感受性パターンを推測することもできますが、正確な亜種同定や感受性検査は専門機関での検査が必要とされています(本邦では千葉大学真菌センターなどへの依頼となると思います)。皮疹が出たり副作用で抗菌薬を変えないといけない時、長期治療になる感染症でもあり、同定/感受性検査はしっかりやっておいた方がいいです。
・治療期間はどうするか
決まりはないですが教科書的には3-6ヶ月とされています。免疫不全の是正ができる患者であれば早期に終了できる可能性はあり、免疫不全が悪化していく患者であればより長期に治療期間を設定する必要があるかもしれません。SOTのガイドラインでも免疫状態によって治療期間を延長し、最低1年はモニタリングせよと記載されています。
参考文献:
Up to dateなど
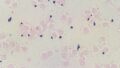
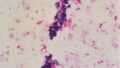
コメント